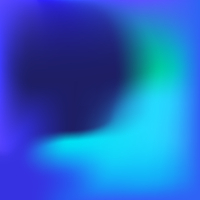レッドブルとマックス・フェルスタッペンのF1復活の鍵はライドハイトか?
F1のサマーブレイク以降、レッドブル・レーシングのパフォーマンスは急上昇しており、マックス・フェルスタッペンは一貫してトップ2フィニッシュを飾り、複数回の優勝を遂げています。この好転は特定のサーキットタイプに限定されるものではなく、チームは様々なコースでの課題を克服してきました。
なぜ重要なのか:
不確実な時期を経てのレッドブルの復活した優位性は、RB21に対する理解が深まったことを示唆しています。多様なサーキットで一貫したパフォーマンスを発揮することは、チャンピオンシップ争いを維持し、将来のシーズンへの足がかりを築く上で極めて重要です。
詳細:
- 新哲学: フェルスタッペンは、この改善が単なる新しいモンツァのフロアによるものではなく、「異なる哲学」によるものだと語っています。これは、データへの盲目的な依存を減らし、ドライバーからのフィードバックをより重視するアプローチです。
- マシンの運用: ヘ Helmuth Marko(ヘルムート・マルコ)氏と Laurent Mekies(ロラン・メキー)氏は、レッドブルが「マシンをどのように運用しているか」を重要な要因として強調しています。
- アンドレア・ステラ氏の理論: マクラーレンのチーム代表である Andrea Stella(アンドレア・ステラ)氏は、レッドブルが空力問題を解決し、特にグラウンドエフェクトを最大化するために、マシンを低いライドハイトで運用する方法への理解を深めたと推測しています。
- ステラ氏は、新しいモンツァのフロアと理解の向上により、レッドブルは現在、より低いライドハイトで運用できるようになり、RB21の潜在能力を最大限に引き出せると提案しています。
- グラウンドエフェクトの基本: グラウンドエフェクトカーは、フロア下部からダウンフォースの60%以上を生成するため、吸引力を高め、気流を密閉するために、可能な限り低く硬く運用する必要があります。
- プランクの摩耗とライドハイト: FIAの技術規則では、プランクはレース後、特定の測定ポイントで最低9mmの厚さが必要であり、1mmを超える摩耗は許容されません。チームはこれらの制限を超えずに、可能な限り低く走行することを目指しています。
- フロントへの摩耗シフト: Sauber(ザウバー)のスポーティングディレクターである Iñaki Rueda(イニャキ・ルエダ)氏は、車のフロント部分でより多くのプランク摩耗を達成したチームが競争上の優位性を得ると指摘しています。これにより、特にダウンフォースが最も生成されるリア部分を、摩耗制限を超えずに低く走行することが可能になります。
- マクラーレンはこの分野で成功を収めており、パドック内ではレッドブルも同様の進歩を遂げているという噂があります。
行間を読む:
ヘルムート・マルコ氏は、レッドブルが今やマシンをより低く走らせることができるかという質問に対し、「間違っていない」と答えることで、ライドハイト理論を間接的に肯定しました。彼はまた、新しいモンツァのフロアがこの効果に大きく貢献したことも認めています。ロラン・メキー氏はより慎重でしたが、モンツァのフロアや「どこでマシンを走らせるかについての広範な探求」を含む「多くの多くの要因」がパフォーマンス向上に貢献したことに同意しました。
今後の展望:
RB21の運用範囲に対するレッドブルの理解の向上と、一貫してパフォーマンスを引き出す能力は、シーズンを力強く締めくくることを示唆しています。この進歩が持続すれば、レッドブルは主要な勢力としての地位を確固たるものにするだけでなく、2025年と2026年のマシン開発に向けた重要な洞察を提供し、将来のチャンピオンシップにおける競争優位性を確保する可能性があります。
元の記事 :https://www.motorsport.com/f1/news/ride-height-key-Red-Bull-and-Max-Verstappen-F...